
借地権付き建物とは?メリット・デメリットや売却方法を解説
公開日:2025年03月17日
この記事では、借地権付き建物について解説します。
この記事では、借地権付き建物について解説します。
借地権付き建物とは、土地の借地権と建物をあわせて購入できる住宅のことです。マイホームを探している人の中には、"借地権"と記載された物件を見たことがある人もいるのではないでしょうか
この記事では、借地権付き建物のメリット・デメリットを解説します。一般的な売却方法やトラブル事例もお伝えするので、購入を検討している人はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 借地権付き建物とは?
- 借地権付き建物の主なメリット・デメリット
- 借地権付き建物の一般的な売却方法
- 借地権付き建物でよくあるトラブル事例
借地権付き建物とは?

ここでは、借地権付き建物の種類を見ていきましょう。
- 普通借地権
- 定期借地権
- 旧借地権
順番に解説します。
普通借地権
1992年に『借地借家法』が施行されたことにより、更新がある借地権は"普通借地権"と呼ばれるようになりました。普通借地権の場合、契約の期間が決められています。満了時に借主が契約終了を申し出る正当な理由がなければ、その後も継続して土地を借りられます。
万が一、契約が終了した際に建物が残っていても、借主は地主に建物買取の請求が可能です。
定期借地権
基本的には契約満了後も土地を借り続けられる普通借地権とは異なり、定期借地権は契約が満了したら土地を更地にして返却する必要があります。1992年の借地借家法の施行によって定められた制度であり、地主にとって確実に土地を返却してもらえるメリットがあります。ただし、借主にとっては、せっかく家を建てても契約満了時に取り壊す必要があり、住宅には不向きでしょう。
定期借地権には、主に以下3種類があります。
借地権の種類と特徴
| 種類 | 契約存続期間 | 用途制限 |
|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | なし |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用建物のみ(住宅は不可) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | なし |
※参考:
契約前に、存続期間や用途制限を確認しておきましょう。
旧借地権
旧借地権は、借地借家法が施行される前の旧法に基づいて設定された借地権です。契約更新が繰り返されやすく、半永久的に土地を借り続けられるため、借主にとってメリットが大きいといえます。
既に契約している旧借地権が、自動的に現行の普通借地権や定期借地権に変更されることはありません。ただし、地主の負担が大きい制度といえます。
可能であれば、再度契約を結び直すなどして調整することがおすすめです。
借地権付き建物の主なメリット

ここでは、借地権付き建物の主なメリットを以下3点から解説します。
- 物件価格が安い傾向にある
- 土地に対して税金がかからない
- 期限を延長すれば長期的に借りられる
順に見ていきましょう。
物件価格が安い傾向にある
借地権付き建物では土地を購入する必要がないため、一般的な不動産に比べて物件価格が抑えられる傾向にあります。住宅購入時の初期費用を抑えたい人や、限られた予算内で物件を見つけたい人にぴったりです。
ただし、住宅を購入したあとも土地の使用量(地代)を払い続ける必要があり、ランニングコストは大きいといえます。
土地に対して税金がかからない
建売住宅や土地付き注文住宅の場合、住宅とあわせて土地を購入するため、土地の固定資産税や不動産取得税などがかかります。
一方、借地権付き建物の場合は土地の所有権は地主が持っています。土地にかかる税金を支払う必要がないため、長期的に支払う税金を抑えられるでしょう。期限を延長すれば長期的に借りられる
借地権付き建物は、条件を満たせば契約を更新して長期間利用できます。特に普通借地権の場合、地主が契約終了を主張できる正当な理由がなければ、契約の継続が可能です。
契約時から満了後の継続を見込んでいる場合は、契約満了後の地代や更新料についてあらかじめ確認しておくと安心でしょう。
借地権付き建物の主なデメリット
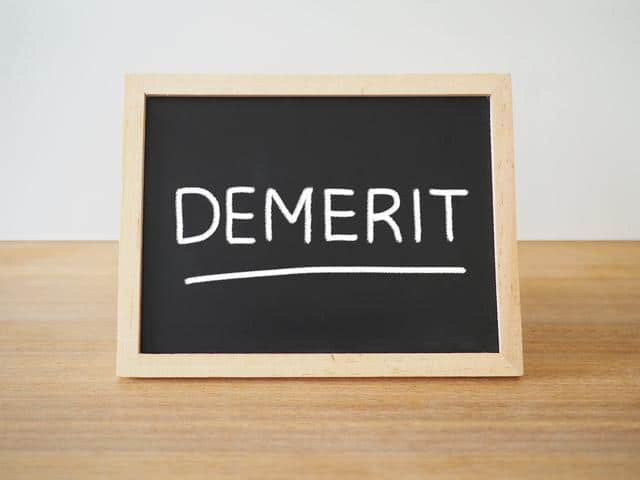
借地権付き建物にはメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。
- 地代を毎月支払わなければならない
- リフォーム・建て替え時・売却時に地主の許可が必要になる
- 住宅ローンの融資が受けられない場合がある
- 借地権付き建物の場合は制約が生じる
上記4点について解説します。
地代を毎月支払わなければならない
借地権付き建物では、土地の使用料として毎月"地代"を支払う必要があります。契約内容によっては、契約期間中でも月々の地代が変動する可能性があります。
地代が変わる可能性の有無や、どのようなケースで変動するのかを事前に確認しておくと安心でしょう。
リフォーム・建て替え時・売却時に地主の許可が必要になる
借地権付き建物の場合、建物の所有権は借主にありますが建物がある土地の所有権は地主が所持しています。そのため、建物のリフォームや建て替え、売却をする際には地主の許可が必要です。許可が得られないとリフォームや建て替え、売却などの計画を進められないため、事前に地主と良好な関係を築いておくことが重要といえます。
住宅ローンの融資が受けられない場合がある
一般的に、住宅ローンを利用して金融機関から融資を受ける際には、土地と建物を担保にします。
借地権付き建物では土地を担保にできないため、通常の住宅ローンを利用できないケースがあります。また、申請時には問題がなかったとしても、審査基準が厳しくなってしまい審査に通らないケースも考えられるでしょう。
一部の金融機関では借地権付き建物にも対応したローン商品を提供しているため、居住地の周辺に利用できる銀行がないか確認しておくと安心です。
借地権付き建物の場合は制約が生じる
借地には、土地の利用に関するさまざまな制約が設けられています。例えば、建築する建物の用途目的や契約更新時の交渉、土地を利用する方法に関する条件などが挙げられます。物件を購入する前に契約内容を十分に確認し、将来的なトラブルを避けましょう。
借地権付き建物の一般的な売却方法

ここでは、借地権付き建物の一般的な売却方法を、以下3点から解説します。
- 借地権を地主か第三者に売却する
- 等価交換の後に売却する
- 地主が所有する借地権とあわせて売却する
順番に見ていきましょう。
借地権を地主か第三者に売却する
借地権付き建物を売却する最も一般的な方法は、借地権そのものを売却することです。地主に直接売却するか、地主の許可を得て第三者に売却するかを選択できます。第三者に売却する場合は借地契約をそのまま引き継ぐ形となりますが、地主の承諾料が必要となるケースがあるため、事前に確認しておきましょう。
等価交換の後に売却する
等価交換とは、建物の所有者と地主が権利を交換して、地土地の一部、もしくは全体を所有してから売却する方法です。借地権から所有権に切り替わるため、売却がよりスムーズになるでしょう。ただし、等価交換には地主との交渉が必要です。実現を目指すためには、計画や条件の調整が重要となります。
地主が所有する借地権とあわせて売却する
借地権付き建物を売却する際、地主が持つ土地の所有権と建物を一緒に売却することも可能です。通常の中古住宅と変わりないため、購入希望者が集まりやすく売買が成立する可能性が高まるでしょう。
ただし、地主に土地の所有権を手放してもらう必要があり、地主の協力が不可欠だといえます。どうしても建物だけで売却できない場合などに検討してみましょう。
借地権付き建物でよくあるトラブル事例

ここでは、借地権付き建物でよく見られるトラブルの事例を以下5点から解説します。
- 借地権付き建物の相続で揉めてしまった
- 建物の売却を地主が許可してくれなかった
- 地主から立ち退きを迫られた
- 地主から地代の値上げを迫られた
- 地権の契約書を紛失してしまった
それぞれ見ていきましょう。
借地権付き建物の相続で揉めてしまった
借地権付き建物を相続する際、相続人同士で権利の分配をめぐるトラブルが起きることがあります。建物の所有権はもちろんですが、借地権にも不動産としての価値があります。
後々のトラブルを避けるためにも、分割方法を早い段階で明確にしておくことがおすすめです。不安な場合は、土地の所有権を持つ地主と相談しながら分割を考えましょう。
建物の売却を地主が許可してくれなかった
先述のとおり、借地権付き建物を第三者に売却する場合には地主の許可が必要です。そのため、地主が建物の売却に承諾しなければ、売却が進みません。
ライフスタイルの変化や家族の事情などで引っ越しをしなければいけない場合には、売却を許可してくれるよう、その旨を地主に丁寧に伝えることをおすすめします。
どうしても許可を得られない場合には、弁護士など専門家への相談を検討しましょう。地主から立ち退きを迫られた
借地の契約を更新するタイミングや契約期間が終了したタイミングなど、地主から立ち退きを要求されるケースがあります。
借地借家法では借主の権利が守られており、正当な理由がない限り地主は立ち退きを請求できません。トラブルを防止するためにも、契約内容は定期的に確認して更新時の交渉を慎重に行いましょう。万が一、不当に立ち退きを要求されていると感じた場合には、弁護士などに相談してください。
地主から地代の値上げを迫られた
地代の見直しについては、基本的には契約時に定められてその旨が契約書にも記載されます。
ただし、過度な値上げを求められた場合には、適正価格を調査した上で地主と交渉しましょう。明らかに不適切な値上げを主張してくる場合には、弁護士を交えた調停に繋がる場合があります。
地権の契約書を紛失してしまった
借地権の契約書を紛失してしまうと、契約内容の確認ができないだけでなく、更新や売却の際に問題が生じることがあります。
その場合、すぐに不動産仲介業者や地主が所持していないか確認しましょう。見当たらない場合でも、地代を支払った証拠になるものを所持しており、建物の登記が完了していれば、借地権の売却は可能です。
万が一のケースに備えて、建物が完成したら早めに借主の名義で登記を実施しましょう。借地権付き建物に関するよくある質問

ここでは、借地権付き建物に関するよくある質問に回答します。
- 借地権付き建物を購入したときの仕訳・勘定項目は?
- 借地権付き建物に相続税はかかる?
- 借地権付き建物を解体した場合の費用は誰が払う?
疑問の解消にお役立てください。
借地権付き建物を購入したときの仕訳・勘定項目は?
借地権付き建物を購入する場合、建物の代金は"建物"勘定で記録しますが、借地権にかかる費用は"借地権"勘定として計上します。また、土地の使用料として支払う地代は"地代"や"賃借料"などの勘定項目で仕訳されます。正確な処理を求める場合には、担当の税理士や会計士に相談しておくと安心です。
借地権付き建物に相続税はかかる?
結論からいうと、借地権付き建物にも相続税は発生します。相続税を計算する際には、借地権とその上に建っている建物を分けて計算する必要があります。借地権の計算では、普通借地権と定期借地権で評価区分が異なる点に注意しましょう。
※参考:
借地権付き建物を解体した場合の費用は誰が払う?
借地権付き建物を解体する場合、原則として建物の所有者である借主が解体費用を負担します。定期借地権の場合でも、契約終了後に土地を更地にして返却する際に建物の撤去に関する費用は建物の所有者が負担します。
ただし、事前に費用負担について地主と取り決めをしている場合はその内容に従いましょう。
借地権付き建物の売買は事前にしっかりと計画を立てよう

この記事では、借地権付き建物について解説しました。借地権付きの建物を売却やリフォーム、建て替えをする場合には、どのような方法でも地主の許可が必要です。
計画がスムーズに進むよう、普段から地主と円満なコミュニケーションを図っておくことが重要です。また、借地権付きの建物にはさまざまな制約が設けられています。契約時に制約内容を確認し、あわせて更新時の手数料や更新後の地代の変動についても聞いておきましょう。

記事監修
加藤 健吾
宅地建物取引士/公認不動産コンサルティングマスター
首都圏10センター以上でのセンター長の他、マーケティング長・総務部長としての経歴も有する。複雑な不動産の資産価値に関し、幅広い知識と経験をもとにアドバイスを提供。
- 2025年1月時点の内容です。














