
住宅の瑕疵(かし)保険とは?種類・保証内容や費用相場について解説
公開日:2025年04月11日
この記事では、住宅の瑕疵保険について解説します。
マイホームの購入を進めている人の中には、「瑕疵(かし)保険」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。瑕疵保険は種類や保証内容に違いがあるため、事前に自分に合う保険とその特徴を知っておくことが大切です。
この記事では、住宅の瑕疵保険の概要や種類、保証内容などを解説します。住宅購入を考えている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 住宅の瑕疵(かし)保険とは?
- 住宅の瑕疵保険の主な種類・保証内容
- 住宅の瑕疵保険の費用相場
- 住宅の瑕疵保険に加入する流れ
- 住宅の瑕疵保険に加入するときの注意点
住宅の瑕疵(かし)保険とは?
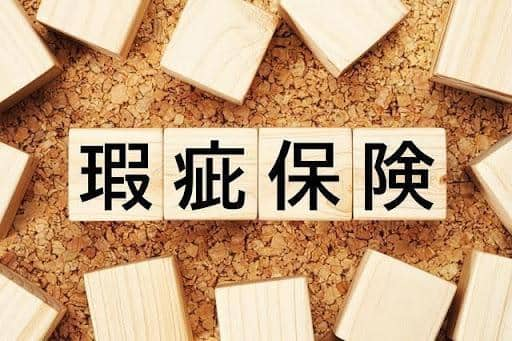
住宅取得から10年以内に瑕疵(欠陥)が見つかり住宅事業者が修繕を行った場合、その事業者に対して保険金が支払われます。
ここでは、住宅の瑕疵保険と瑕疵保証との違いを見ていきましょう。
参考:
住宅瑕疵担保履行法とは丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
瑕疵保証との違い
瑕疵保証とは、購入から一定期間内に見つかった重大な欠陥に対して、住宅事業者が無償で修繕をする保証のことです。重大な欠陥とは、家の構造耐力上主要となる部分や雨水の浸入を防止する部分のことを指し、住宅事業者には10年間の保証責任が定められています。
ただし、住宅事業者が倒産などによって修理できなくなった場合、住宅取得者が自分で修理や建て替えを実施するなど、経済的に大きな負担になってしまうケースが見られました。
そこで、2007年に『住宅瑕疵担保履行法』が成立し、住宅の瑕疵保険制度が成立しました。現在は、住宅事業者が保険に加入して修理費用を十分に賄える状態になった上で、新築住宅を引き渡すよう決められています。
参考1:
住宅瑕疵担保履行法とは丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
参考2:
住宅の瑕疵保険の主な種類・保証内容

ここでは、以下4種類から住宅瑕疵保険の保証内容を見ていきましょう。
- 住宅瑕疵担保責任保険(新築の場合)
- 既存住宅売買瑕疵保険(中古の場合)
- リフォーム瑕疵保険
- 大規模修繕工事瑕疵保険
住宅瑕疵担保責任保険(新築の場合)
新築住宅で住宅瑕疵保険に加入する場合、工事中に検査が実施されます。
検査のタイミングは、基礎配筋工事が完了したときや駆体工事が完了したときなどであり、回数は住宅の規模によって異なります。
保険の内容は、注文住宅の場合は工事請負契約の際に、建売住宅の場合は売買契約の際にしっかりと確認しましょう。なお、保険の申し込みは事業者が行います。
住宅取得者は、住宅の引渡しから10年以内に瑕疵が発見されたにもかかわらず、事業者の倒産などの理由により修理を受けられない場合、保険法人に対して直接、保険金の支払いを請求することが可能です。
支払われる保険金の上限は2,000万円であり、事業者が倒産した場合の填補率は100%です。たとえば、以下のように計算できます。戸建て住宅に欠陥が見つかり、補修や引っ越しなどに1,000万円がかかったとき
- 保険支払額=(1,000万円-10万円(免責金額))×100%=990万円
なお、対象となる費用には補修に伴う引っ越し費用や仮住まい費用、調査費用などが含まれています。
参考:
既存住宅売買瑕疵保険(中古の場合)
中古住宅の場合には、既存住宅売買瑕疵保険を利用します。中古住宅の検査と保証が合わさった保険であり、加入するためには該当住宅が専門建築士の検査に合格することが必要です。
そのため、既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅は、構造上のリスクが低く安全に居住できる物件だといえます。
また、万が一購入した物件に構造上の欠陥が見つかった場合には、補修費用などにかかった費用が事業者、もしくは買主に支払われます。
保険金額は最大で1,000万円であり、填補率は100%です。免責金額は原則として5万円と定められています。
ただし、新築住宅の保険期間が10年間であるのに対し、中古住宅の場合は最長でも5年間である点に注意しましょう。
参考1:
参考2:
既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ、仲介事業者保証型)丨国土交通省
リフォーム瑕疵保険
リフォーム工事を対象とするリフォーム瑕疵保険は、リフォーム工事の検査と保証が一体となっています。
保険への加入を希望する場合、住宅瑕疵担保責任保険協会のページで公開されている事業者にリフォームを依頼しましょう。工事中や工事完了後に第三者の建築士が検査を実施するため、確実に質が高い工事を受けられます。
万が一、リフォーム工事のあとに欠陥が見つかった場合には、保険法人から事業者に修繕費用が支払われます。事業者が倒産している場合、費用を受け取るのは工事発注者です。
リフォーム瑕疵保険の期間は保険商品によって異なりますが、最大で10年となっています。また、保険金額は100〜2,000万円となっていますが、請負金額などによって異なります。
事業者が保険金の支払いを受ける場合は填補率が80%ですが、工事発注者の場合は填補率が100%です。また、免責金額は10万円となっています。
参考1:
参考2:
大規模修繕工事瑕疵保険
マンションなどの大規模修繕工事に対しては、大規模修繕工事瑕疵保険の利用が可能です。
マンションなどの修繕工事で瑕疵があった場合、事業者は保険法人から保険金を受け取り、工事発注者に対して瑕疵担保責任を負担できます。事業者が倒産している場合には、発注者が保険金を受け取ります。
保険期間は基本的に5年間であり、特約に該当する場合は10年間です。保険金は工事請負金額などによって異なりますが1,000万円〜5億円となっており、免責金額は10万円です。
また、事業者が受け取る場合の填補率は80%で発注者が受け取る場合は100%となっています。参考1:
参考2:
住宅の瑕疵保険の費用相場

ここでは、住宅瑕疵保険の加入費用相場を解説します。
- 新築住宅の費用相場
- 中古住宅・リフォームの費用相場
新築住宅の費用相場
新築住宅の場合、瑕疵保険に加入する際の費用は家の延床面積によって異なります。以下の表に延床面積ごとの保険費用例をまとめたので、見ていきましょう。
| 住宅の延床面積 | 保険料 | 検査費用 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 〜100㎡ | 4万800円 | 2万6,290円 | 6万7,090円 |
| 100〜125㎡ | 4万6,600円 | 2万7,940円 | 7万4,540円 |
| 125〜150㎡ | 5万3,000円 | 3万910円 | 8万3,910円 |
| 150〜180㎡ | 6万300円 | 3万4,430円 | 9万4,730円 |
| 180㎡~ | 7万6,200円 | 3万8,170円 | 11万4,370円 |
参考:
※保険金額2,000万円の場合
新築住宅の場合、加入時の費用相場は6〜12万円程度だといえます。ただし、保険法人やプランなどによって異なるため、加入予定の法人の料金表などを確認しましょう。中古住宅・リフォームの費用相場
中古住宅の場合、瑕疵保険の加入費用は延床面積や保険期間、保険金額などによって異なります。保険期間が5年間で特約を付帯しない木造住宅の場合、加入時の費用例は以下のとおりです。
| 住宅の延床面積 | 保険料 | 検査費用 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 〜100㎡ | 3万8,500円 | 2万3,100円 | 6万1,600円 |
| 100〜125㎡ | 4万2,900円 | 2万3,100円 | 6万6,000円 |
| 125〜150㎡ | 5万2,500円 | 2万4,200円 | 7万6,700円 |
| 150〜200㎡ | 6万7,900円 | 2万5,300円 | 9万3,200円 |
参考:
JIO 既存住宅かし保険(宅建業者用)料金表丨JIO 日本住宅保証検査機構
上記から、既存住宅瑕疵保険の加入費用相場は6〜10万円程度だといえます。
また、リフォーム瑕疵保険の場合は工事内容やその金額によって加入時の費用が以下のとおり異なります。
| リフォーム工事内容 | 請負金額 | 検査回数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| キッチンの交換工事 | 80万円の場合 | 1回 | 3万3,930円 |
| 外装(屋根・外壁)の全面改修工事 | 180万円の場合 | 2回 | 5万4,360円 |
| 間取りの変更 | 550万円の場合 | 2回 | 6万6,100円 |
| 部屋の増築と内装工事 | 1,200万円の場合 | 4回 | 9万1,030円 |
参考:
JIOリフォームかし保険 料金表丨JIO 日本住宅保証検査機構
上記の表から、リフォーム瑕疵保険の場合は加入費用相場が3〜10万円程度だといえます。
住宅の瑕疵保険に加入する流れ

ここでは、住宅の瑕疵保険に加入する流れを見ていきましょう。
- 新築住宅の場合の流れ
- 中古住宅・リフォームの場合の流れ
新築住宅の場合の流れ
ここでは、新築注文住宅の場合に住宅瑕疵保険に加入する流れを解説します。以下に流れをまとめたので、確認しましょう。
- 着工前準備:現地調査の実施
- 設計:利用する保険法人の設計施工基準を満たすように設計
- 工事請負契約の締結
- 確認申請
- 確認通知
- 保険契約申し込み:利用する保険法人で契約の申込手続きを実施
- 着工:利用する保険法人の基準を満たすように施工
- 現場検査:検査回数は住宅によって異なる
- 保険証券の発行申請:利用する保険法人で保険証券発行申請
- 引き渡し:住宅取得者に保険付保証明書などを発行
参考:
保険加入手続きの流れ丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
中古住宅・リフォームの場合の流れ
既存住宅瑕疵保険に加入している住宅を購入する方法は、誰から家を買うかによって異なります。売主が不動産会社などである場合、住宅瑕疵担保責任保険協会のページで瑕疵保険に加入している事業者を検索しましょう。この事業者が販売している住宅であれば、瑕疵保険での検査や保証を受けられます。
個人が売主の場合、先程のぺージから中古住宅の検査や保証を行っている機関を検索し、依頼できます。
また、リフォーム瑕疵保険に加入する場合、手続きを行うのは工事発注者ではなく事業者です。
リフォーム瑕疵保険に加入している事業者を検索して工事を依頼して、保険による検査や保証を受けましょう。参考1:
参考2:
安心してリフォームするなら「リフォームかし保険」!丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
住宅の瑕疵保険に加入するときの注意点

ここでは、住宅の瑕疵保険に加入する際の以下4つの注意点を解説します。
- 加入前に検査を受ける必要がある
- 保証の対象範囲が決まっている
- 旧耐震基準の建物は対象外になるケースがある
- 住宅ローン控除の条件に瑕疵保険の加入は含まれない
加入前に検査を受ける必要がある
瑕疵保険に加入するには、専門家による検査を受ける必要があります。
住宅の構造や防水性能などが基準を満たしているか確認され、基準に適合しない場合は修繕や再検査が必要です。
検査にかかる時間を考慮し、スケジュールに余裕を持って手続きを進めることが大切です。保証の対象範囲が決まっている
瑕疵保険でカバーされる範囲は、住宅の構造に関わる部分や雨漏りを防ぐ部分など、基本的な部分に限定されています。
内装や設備の不具合は対象外となるケースが多く、保証の範囲を事前に確認しておくことが大切です。また、保険期間は住宅や工事内容によって異なり、期間外に見つかった瑕疵は保証対象外となります。
旧耐震基準の建物は対象外になるケースがある
現行の耐震基準は1981年6月から施行され、これより前に建てられた建物は旧耐震基準に基づいて建築されています。
現在の耐震基準を満たしていない場合には、瑕疵保険の対象にならないでしょう。ただし、1981年5月以前に建てられた住宅でも、補強工事などによって耐震基準を満たしている場合には、保証対象になる可能性があります。
住宅ローン控除の条件に瑕疵保険の加入は含まれない
中古住宅の購入で住宅ローン控除を利用する場合、以前は構造ごとの築年数を満たしていることや瑕疵保険に加入していることが必要でした。
しかし、2022年の改正によって、1982年以降に建築された住宅であれば、住宅ローン控除を受けられるようになっています。現在は、住宅ローン控除の利用に瑕疵保険の加入は義務付けられていないため、ローン控除の利用を検討している人は注意しましょう。
参考:
住宅の瑕疵保険に関するよくある質問

ここでは、住宅の瑕疵保険に関するよくある質問に回答します。
- 住宅瑕疵担保責任保険は誰が払う?
- 中古住宅の瑕疵保険がいらないといわれる理由は?
- 中古住宅で瑕疵保険に入れないケースは?
住宅瑕疵担保責任保険は誰が払う?
住宅瑕疵担保責任保険の費用を負担する人について、法律上の明確な規定はありません。誰が負担するかについては、住宅取得者と事業者で事前に相談して決めます。
また、中古住宅の個人間売買では費用負担に関するトラブルが発生しやすいため、契約書に明記しておくことがおすすめです。
中古住宅の瑕疵保険がいらないといわれる理由は?
中古住宅の瑕疵保険に加入するためには、専門家による検査に合格する必要があります。検査に合格しても対象となるのは、構造上の主要部分や雨漏りを防ぐ部分に限定されます。
内装や設備の不具合は対象外となるため、保険の必要性を感じない人もいるでしょう。中古住宅で瑕疵保険に入れないケースは?
1981年以前に建築された中古住宅の場合、現行の耐震基準を満たしていなければ瑕疵保険に加入できません。
また、床が傾いていたり外壁が大きくひび割れていたりするなど、既に構造上の大きな問題がある場合も、加入できないおそれがあります。
不安がある場合には、加入手続きを進める前に専門家へホームインスペクションを依頼することがおすすめです。住宅の瑕疵保険は建物の不具合・欠陥に備える上で重要

この記事では、住宅の瑕疵保険について解説しました。
住宅の瑕疵保険は、購入後の一定期間内に見つかった欠陥について保険金が支払われる制度です。加入するには検査に合格する必要があるため、質の高い住宅確保にも繋がります。
また、保険の種類や保証内容、保険期間などは利用する保険法人やプランによって異なります。契約時に内容をしっかりと確認し、想定外のトラブルを防ぎましょう。

記事監修
山口 靖博
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
最新のトレンドや法改正を踏まえ、円滑な住宅売買に向けた仕組み作りと前線でのサポートを実践する。「ちんたいグランプリ(旧・不動産甲子園)」 2020年度・2022年度特別賞。
- 2025年3月時点の内容です。














